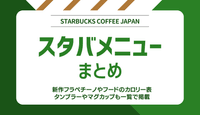椿の剪定はいらない枝を付け根からバイバイ!真夏のイメチェンと同じ
真冬に美しく咲く椿は、昔からお庭の花として、茶人や武士に愛されてきました。
日本原産の花ですが、海外にも輸出され、「椿姫」としてオペラの題材にもなっています。
お庭に咲いていたら素敵な和風な感じ…とあこがれてる方も多いはず。
ここではそんな椿の花をよりよい環境で育て、より美しく見せるための剪定方法をご紹介します!
目次
椿に剪定が必要な理由

まず、剪定とは、植木の枝を切ることで形を整えたり、風通しを良くする庭木のお手入れのことを指します。
椿に剪定が必要な理由は、
・風通しをよくするため
・形を保つため
この2つです。
成長段階で枝や葉が増えると、風通しが悪くなり、蒸れてしまいます。
このことが、虫や病気が発生する原因となり、椿が傷んでしまう可能性も。
それゆえ、通気性を良くする必要があり、剪定をするべきなのです。
また、椿の成長を放置すると、大きくなりすぎてお手入れがしにくくなったり、栄養が行き届かず成長の妨げになることも。
適切な管理をして、毎年美しい花を咲かせるために、椿には剪定が必要なのです!
ちなみに、剪定には大きく分けて2つの種類があります。
・透かし剪定:不要な枝を付け根から切って、全体的な枝の量を減らして風通しをよくするもの。
・切り戻し剪定:枝を途中から切って、短くして樹形をコントロールするもの。
椿の場合、まず透かし剪定で風通しを良くして、その後に切り戻し剪定で、全体の形を整えるのが一般的。
椿剪定はいつするのがいい?

椿の剪定は、ただすればいいというわけではありません。
適切な時期があるのです。
その時期とは、花が咲き終わった4月~5月頃。
そもそも椿は2月~4月に開花し、次の年の花になる芽(花芽)が6月頃に出始めます。
芽が出てしまうとそれを切り取ってしまい、翌年に花が咲かない原因になることがあるので、剪定はそれまでの期間。
4~5月に行うのがオススメなのです!
剪定する枝や葉は7タイプ

剪定の目的は風通しをよくするためですが、どれでも切っていいってわけでもないんです。
というわけで、はじめに剪定する際に切るべき枝・切ってもいい枝をご紹介します!
チャドクガの卵がついた葉っぱの枝
チャドクガという害虫は毒をもっていて非常に危険。
黄色い卵(これも毒がある)のうちについた葉っぱの枝ごと切り戻し剪定します。
徒長枝
こちら、「とちょうし」って読むんです。
これは分かれた枝が無く、1本だけ主幹の下の方から他の枝よりも長く伸びた枝のこと。
全体のバランスも悪くなるので切っちゃいましょう。
内側に伸びている枝
内側、つまり主幹に向かって伸びている枝。
これはそのままにしておくと中心が混みあってしまうため不要です。
交差している枝
他の枝と交差している枝は、どちらかを切った方がすっきりします。
葉も芽もない古い枝
葉も芽もない古い枝は途中から切ってしまうと、そこから枯れやすくなってしまいます。
根元からバッサリ切りましょう。
何叉かに分かれている枝
枝先が何叉かに分かれている枝も風通しが悪くなってしまう原因。
その分かれ目から1本だけ残るように切ります。
葉
1本の枝の同じところから複数の葉が生えている場合もあります。
2~3本ほどを残して、その他の葉を付け根から切りましょう。
だいたい切る順番に並べてみました。
この7タイプを頭に入れておけばOKです。
椿剪定の方法

いよいよ、剪定を行う方法を紹介しますね。
・長袖、長ズボン、レインコートなど肌を覆うもの
・ビニール袋
・新聞紙
・剪定ばさみ
・剪定ノコ
・殺菌剤
おすすめ
[PR]

軟膏のように木の切り口に塗りつけて殺菌し、病原菌が入るのを防ぎます。
評判もよく、木ならなんでも使えるので、お庭がある方にはオススメです。
なぜか色はどぎついオレンジですが…。
剪定の作業は危険なので、必ず軍手をはめましょう!
チャドクガの卵には毒性があるので、皮膚につかないよう長袖長ズボン、レインコートなどを着用しましょう。
もしチャドクガの卵が見つかったら枝ごと切り取って、ビニール袋に入れて捨てます。
また、枝や葉が散らかってしまうので、木の下に新聞紙やビニールシートを敷くのがおすすめ。
花数を多く楽しむか、樹形を作るか決めましょう!
花をいっぱいつけたいなら、あまり樹形は作らず、いらない枝だけ1本1本切っていくとよいです。
樹形重視の場合は刈り込みますが、苗木から育てると完成まで数十年かかるとか。
椿の木は全体の形をダイヤ型、ひしがたに見立てて切ると、きれいに仕上がると言われています。
まずは、切ってもいい枝として紹介した、
・徒長枝
・内向きに伸びてしまった枝
・葉も芽もない枝
・他の枝と交差した枝
・何叉かに分かれている枝
これらの枝をその付け根から切り落とします。
枝が込み合ってる場合は絡み合う枝をほぐしてくださいね。
細い枝の場合は剪定ばさみを、太い枝の場合は剪定ノコを使って、切り落としましょう。
全体の形をととのえます。
芽あるいは葉のついてる数mm上で切りましょう!
これで徒長枝が生えないようになります。
また椿は葉も、芽もない「枝の途中」で切るとそこから枯れやすいので注意してください。
ここまでの作業が終わっても、まだ内側が混雑している場合は、短めの枝を剪定しましょう。
芽のついてる数mm上で切ると、徒長枝が生えるのの予防になります。
切りすぎには注意!全体の日当たりや風通しがよくなる程度にしましょう。
葉っぱの量が多い場合も、少し減らしましょう。
目安としては、同じ部分から何枚か生えている葉の1枚を切る程度。
葉を減らしすぎると枯れてしまう可能性があります。
減らしすぎに注意しましょうね!
切った部分から菌などが入って木が病気になるのを防ぐために、切り口に殺菌剤をつけましょう。
下に敷いた新聞紙ごと木の下に落ちた枝と葉を片付けましょう。
残った枝と葉は、ほうきとちりとりでお掃除。
これで完了です。
剪定お疲れさまでした!
絶対に失敗したくない時はプロに頼もう

「大事な椿、絶対に失敗したくない。」
「不器用で自信がない。」
そんな方はプロに頼んでしまうのがオススメですよ!
プロに頼むメリット
専用の道具や作業着を用意して、作業するのはなかなか大変。
だったらプロにお任せしてしまいましょう。
プロは高い技術と豊富な知識で剪定を行ってくれます。
普段のお手入れのコツも聞くことが出来るし、1年に1回プロと会ってお話をすることでより健康的に育てることができますよ!
プロの剪定の費用・かかる時間は?
プロに頼むとなると、気になるのがその費用と時間。
相場は、3,000〜5,000円。(木の状態によって変動あり。)
何社かお見積もりを出してもらうといいでしょう。
かかる時間ですが、一般的な家庭のお庭なら1日程度で作業は完了します。
自分でやるより綺麗にできて、その分他のことに時間を使える。
初心者の方はプロに頼むのもいいかもしれませんね!
椿の成長を左右する日頃のお手入れ3つ

剪定することで椿は健康でいられます。
しかし、椿を元気にして、いっぱい花をつけるためには、毎日のお世話も大切。
具体的には
・肥料
・虫よけと病気予防
この3つ。
水やり
鉢植えの場合、基本的に表面が乾いたら鉢底から水があふれ出るくらい水をあげましょう。
頻度の目安は、季節ごとに異なります。
・春:2日に1回
・夏:朝夕2回
・秋:2日に1回
・冬:3日に1回
お庭に直接植えている場合、水やりの必要はほとんどありません。
夏場に暑くて乾燥している場合は、たっぷりの水をあげましょう。
肥料
肥料を与える時期は、年に2回。
・3~5月
→植物が花や実を付けた後、消耗したエネルギーを補うための肥料
・9~11月
→冬向けて体力を蓄えるための肥料
どちらも緩効性の肥料または油かすなどをあげるといいでしょう。
ホームセンターや園芸店で手に入ります。
おすすめ
[PR]

緩効性の肥料でよく効き、ニオイもなく軽いのでとても扱いやすいです。
室内の植物にも安心して使えます。
IB肥料は農家でも使われているんですよ。
害虫と病気の予防
植物の大敵、害虫と病気。
それぞれの特徴とその対処法について紹介していきますね!
チャドクガ
剪定のところでも出てきましたが、椿栽培はこれとの戦いといっていいほどの虫です。
ツバキ科の植物を専門としている害虫で、ほかの植物ではあまり聞きません。
葉を食べてしまい、放置していると椿の木が丸裸に。
また、卵・幼虫・成虫ともに毒を持つ毛を全身にはやしていて、これが私たちの皮膚に刺さるとかゆみをともなう発疹が出ます。
治るのに1か月くらいかかるとか…。
一番活発で害の大きい幼虫の発生時期は4~5月と9月下旬ごろの2回。
葉っぱに卵が産みつけられるので剪定して発生を抑えるのが一番。
春の剪定に加えて、8月にも軽く剪定をしておきましょう。
剪定した後、オルトラン系やベニカ系の薬剤を散布すると幼虫の発生をかなり防げます。
幼虫が発生した場合、髪の毛も含め完全防備したうえで薬剤を散布しましょう。
チャドクガの毒針がおれてささると怖いので、毒針凝固剤がオススメ。
死んだ幼虫は毒針が皮膚に刺さらないよう気を付けてビニール袋に密封して捨てます。
おすすめ
[PR]

毒針ごと虫を固めてくれるので、針が刺さる心配なし。
殺虫成分がないので、副作用を気にせず、安心して使用できますね。
マイナス点としては1本じゃ全然足りない!
少しお高いですがまとめ買いしましょう。
カイガラムシ
すす病という黒いカビが葉に広がり、光合成できなくなってしまう病気の原因に。
また、樹液を吸うことで木の健康を害します。
専用の薬剤で駆除しますが、成虫になるとあんまり効きません。
歯ブラシや割りばしでこすり落としましょう。
おすすめ
[PR]

ジェット式なので、水でうすめるなどの手間がいらず、手が汚れないアイテム。
これなら成虫にも効くかも?
カイガラムシはかなりポピュラーな害虫なので、ガーデニングをやる方は1本もっておいいですね。
花腐菌核病
花びらに茶色の斑点が出てしまう病気。
雨に当たると被害が広がります。
花が地面に落ちると翌年の病気の発生源に。
病気になった花は早くつんでしまいましょう。
流れる水で病気が他の花びらにうつるので、水やりも花びらにはかからないようにします。
普段のお世話で椿を元気に保って、冬きれいに咲く姿を見られるようにしましょう!
椿を購入するときのポイント

ここからは、初めて椿を買う、または買った、そんなみなさんへのコーナー。
元気な椿を育てるために、お手入れだけでなく、購入の段階からポイントをおさえておきましょう。
そのポイントは、2つ。
・苗選び
・植え替え
では、まずは苗の選び方から!
苗選び
椿って苗も結構いろいろあって、選ぶのが大変。
実は椿の苗選びってかなり重要なんです!
そのポイントは、
・苗木の色に注目
・品種説明を確認
・接ぎ木苗を選ぶ
詳しく解説していきますね♪
苗木の色に注目
苗全体が黄色いもの、つぼみが極端に多いものは避けましょう。
椿自体が弱っていたり、肥料不足の可能性が。
ただし、品種によっては黄緑の葉の品種もあるので、注意してくださいね!
品種説明を確認
椿の苗を選ぶとき、品種名と品種説明・開花時期の表示があるラベルが付いているものを選びましょう。
品種説明が明確であるものほど、良質な椿であることが多いですよ♪
接ぎ木苗を選ぶ
椿の苗は挿し木苗と接ぎ木苗の2種類があります。
接ぎ木苗:さざんかや乙女ツバキなどの台木に椿を接いだもの。
一般的に流通しているのは挿し木苗ですが、オススメするのは接ぎ木苗。
接ぎ木苗は、成長が早く、どんな土壌にも対応できる強さがあります。
品種により違いはありますが、接ぎ木苗は1年で、挿し木苗の2年~3年分の成長をするとか。
花付きの良さも挿し木苗に比べ良く、活け花や切り花として剪定をしても安心です♪
植え替え
さて椿の苗を買って、一番にすることってなんだろう?
その答えは植え替え。
どの植物も買ったときに入ってる鉢は小さめのことが多いです。
根が鉢いっぱいに張っていませんか?
新しい鉢やお庭に植え付けてあげましょう。
時期は花後の3月中旬~4月、花芽(成長すると花になる芽)が固まる前の9月中旬~10月中旬が最も適しています。
鉢植えとお庭に直接植える2つの方法を説明しますね!
鉢植えの方法
・鹿沼土(中粒)
・赤玉土(中粒)腐葉土2の割合で混ぜたもの
・緩効性肥料
・一回り大きな鉢(1号上のサイズ)
鉢底アミを鉢の底の穴にかぶせるように敷きます。
底が見えなくなるくらいまで、鹿沼土(大粒)を敷きます
赤玉土(中粒)6:鹿沼土(中粒)2:腐葉土2の割合で混ぜたものを鉢の1/5程度入れます。
根についた土を一回り崩して、苗を入れます。
混ぜた土を、苗の根についた土の高さまで入れます。
入れ終わったら軽く割りばしなどで固めます。
水をあげて根を土になじませます。
表面に緩効性肥料を置きます。
日陰に1週間置いて環境に慣れさせてあげましょう。
地面に直接植える方法
水はけのよい西日の当たらない半日陰の場所に植えましょう。
多少水持ちがよい場合は鹿沼土を混ぜて改良しましょう。
・大型のシャベル
・小型のシャベル
・支柱
・ビニールハンド
根鉢の直径2倍ほどの広さ、根鉢と同程度の深さの穴を掘りましょう。
掘り起こした土と腐葉土を混ぜます。掘り起こした土7:腐葉土3くらいの割合です。
混ぜた土の3割ほどを穴に入れましょう。
苗を植えます。
根についた土を1/3程度軽く崩した後、混ぜた土の上に置きます。
残りの土を根鉢の高さまで入れます。
土をシャベルなどで固め、苗がぐらつかないようにします。
きちんと根が張るまでは、支柱を添えるのがいいでしょう。
椿の木にピッタリと沿うように支柱を挿し、ビニールバンドで数か所留めます。
水をあげて、土に苗をなじませます。
緩効性肥料を表面に置きましょう。
これにて完了です!
まとめ
いかがでしたか?
椿剪定は、
・芽を切り落とさないために4〜5月に行うこと
・木の成長を弱めないために枝も葉も切りすぎないこと
この2つを気をつけていればOK。
椿の元気な成長のために必要不可欠な椿剪定。
ぜひ、チャレンジしてみてくださいね!