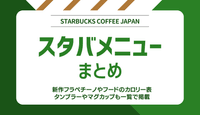ヤマボウシの剪定方法!気を付けるべきは時期と花芽を見分けること!
白い花を咲かすヤマボウシ、とっても綺麗ですよね。
お家のシンボルとして育てている人も多いと思います。
そんなヤマボウシのお手入れに、困ったことはありませんか?
すくすく成長してるからいいやー!と放置していると、衛生的によくないんです。
ヤマボウシは、定期的に剪定をしましょう!
でも剪定って、なんだか本格的に聞こえて、大変そう…って人も多いはず。
でも大丈夫です!
気を付けるべき点を抑えれば、簡単に剪定ができちゃいます!
今回はみなさんに、
・ヤマボウシの剪定のメリット
・剪定するべき枝
・ヤマボウシの剪定方法
・花が咲かないとき&うどんこ病
などついてご紹介します!
これを読んで、ヤマボウシを健康的に育てましょう!
目次
ヤマボウシの1年間

真っ白な4枚の花びらを咲かすヤマボウシ。
開花時期は5~6月で、そのあとの9~10月にかけて実がなります。
ヤマボウシは落葉樹なので、冬に入る前の11月にその葉をすべて落とします。
冬は次の年にそなえて、お休みするわけですね♪
ヤマボウシを剪定するメリット

剪定とは余分な木の枝を切ることです。
剪定をしないまま放っておくと、ヤマボウシの枝は伸び放題。
ヤマボウシにとって、剪定はとっても大切なんです!
剪定をするメリットとしては、
・光が届くようになる
・風通しが良くなる
・養分が効率よく回る
・害虫の温床が予防できる
・見栄えが良くなる
ことなどがあげられます!
衛生的にも、見た目的にも、剪定はぜひ行いたいですね!
ヤマボウシの剪定で注意すべきこと!

ヤマボウシの剪定をする前に、まず気つけるべきことについて知っておきましょう!
気を付けるべきことは、
・剪定の時期
・枯れた枝はそのままにしない
・花芽と葉芽の見分け
の3つです!
剪定の時期を守ろう
ズバリ、ヤマボウシの剪定に適した時期は、11月下旬~2月です!
この時期は、ヤマボウシが休眠しているため、剪定による負担が少なくなるんです!
この休眠前の秋までに体内に十分な養分を蓄えているので、太い木を切っても傷める心配はありません。
枯れた枝は放っておかないようにしよう
枯れた枝は、腐ったものが好きな害虫の住みかになってしまいます。
こまめに枝の様子をチェックして、枯れている枝があったら、時期に関わらず取り除いてくださいね!
花芽(はなめ)と葉芽(はめ)を見分けよう
花芽とは花になる芽、葉芽とは葉になる芽のことです。
(文字通りの意味ですね!)
花芽を切ってしまうと、来年花が咲かなくなっていしまいます!
剪定時期の11月頃は、花芽も葉芽もついているので、花芽を切らないことに注意しましょう!
でも花芽と葉芽ってすぐに分かるの?って疑問に思いますよね。
安心してください!
見た目で判断できます!
花芽と葉芽はそれぞれ、
・花芽はふっくらしていて大きい
・葉芽はツンととがっていて、締まっている
という特徴があります。
以上の3点に気を付けて剪定しましょう!
ヤマボウシで剪定すべき枝

「剪定はしたいけど、実際どんな枝を切ったらいいのかわからない…。」
という方も少なくないと思います。
ですので、まずは剪定すべき枝について紹介しますね!
ヤマボウシの剪定すべき枝は、
・徒長枝(とちょうし)
・不自然な向きに生えた枝
の3つです。
ひこばえ
木の根元から出てくる細い枝のことです。
ひこばえがあると、ヤマボウシ全体の見た目が悪くなってしまいます。
同時に栄養が根元で消費されて、上部まで行き届かなくなってしまうのです。
徒長子
樹木の幹や枝から飛び出るように真上に伸びた枝のことです。
害虫が住み着く原因となってしまいます。
また、雨風に弱く、折れやすいので危険なんです。
不自然な向きに生えた枝
不自然な向きに生えた枝とは、
・正常に伸びた枝と交差する枝
・幹の方に逆向きに伸びる枝
・横に伸びた枝から下に伸びる枝
などです。
これらの枝は、他の枝の成長を妨げます。
また、景観も損ねてしまいますよね!
以上のひこばえ・徒長子・不自然な向きの枝が剪定すべき枝です。
…どうですか?少しわかってきましたでしょうか?
剪定するべき枝を紹介したところで、早速剪定してみましょう!
ヤマボウシ剪定であったら便利な道具

続いて、ヤマボウシを剪定するときの便利グッズをご紹介します。
必須ではないんですが、あると剪定がスムーズに進むと思いますので、チェックしてみてくださいね。
●脚立・はしご
ヤマボウシの木の高さによっては、高いところでの作業が必要になるかもしれません。
特に、剪定バサミで高いところの小さな枝を切るときには、近くで作業したいこともあるはずです。
そのための脚立やはしごですが、安全に作業することを考えると、三脚の脚立がオススメです。
庭木の剪定は、足場がコンクリートなどとは違い、水平でなかったり凹凸があったりと、安定しない可能性が高いでしょう。
そのため、支点が3つの脚立の方が、傾かないし倒れにくいんです。
脚立はあって困るものではありませんが、置き場所、収納場所も考えてサイズを選ぶといいでしょう。
●高枝切りバサミ・高枝ノコギリ
高いところの枝を切りたいとき、脚立やはしごを用意しなくてすむ方法があります。
CMで有名な「高枝切りバサミ」や「高枝ノコギリ」ですね。
どちらも、手が届かない高い場所の枝を切るときに使用します。
高枝切りバサミは、手元のグリップでパイプの先に付けられたハサミを操作するタイプが多いので、使いこなすには少し慣れが必要です。
高枝ノコギリは、太い枝を切りたいときに便利です。腕くらいの太さなら簡単に切れるものが多いようですね。
ただ、初めて使う場合は、切りやすい「刃が厚くて軽量のもの」をオススメします。
●熊手・竹箒・ちりとり・ゴミ袋・紐
剪定すると、たくさんの枝を処理しなければなりません。
そのため、庭掃除の道具があると便利です。
熊手や竹箒は、落ち葉をかき集めるのに便利ですから、ヤマボウシの葉が落ちる時期にも活躍します。
しゃがんでの作業は腰を痛めますので、立ったまま作業できるお掃除グッズがあると助かりますね。
それから、剪定した枝葉をゴミに出す方法は、お住まいの自治体によって違うはずです。
枝の場合、ゴミ袋に入れず紐で縛っただけでも大丈夫な自治体もありますので、ゴミ袋を節約したい場合はゴミ捨てルールについて調べてみましょう。
●傷口癒合剤
これは、木の剪定を行ったときに傷口を守る薬です。
切り口からは水や樹液が出て、庭木が弱ってしまい枯れやすくなることがあるため、この薬を塗って傷をふさいで保護することができます。
とはいえ、全ての切り口に塗るのは大変ですので、中指くらいの太さの枝を剪定したときに、傷口に塗ってあげるといいでしょう。
ヤマボウシを剪定してみよう!

それでは実際に剪定をしてみましょう!
・園芸用手袋、または軍手
おすすめ 商品

こちらの商品、錆びにくい素材で作られているため、いつまでも切れ味よく使うことができます。
滑り止めのハンドルが軽く、握った感触とフィツト感が抜群なのでおすすめです!
専用のハサミが手に入りましたら、早速切っていきましょう。
枝を触るので、けがをしないように園芸用手袋または軍手を忘れずにしましょう!
枝を切りやすいように、絡まっている枝同士をほぐしましょう。
先ほど説明した、ひこばえ・徒長子・不自然な向きの枝を剪定ばさみで切り落としましょう!
根元から思い切ってカットしてくださいね♪
枯れた枝は枯れている部分だけ、切ってしまいましょう。
親指くらいの太さまでの枝なら、手で折ることもできます!
手順はこれで終わりです!
ここからはちょっとおまけです。
植物を育てているときに、うまくいかないことってありますよね?
そんなお悩みを解決しちゃうコーナーです!
ヤマボウシのトラブルあれこれ

ヤマボウシを育てているときに起きてしまいそうなトラブル、
・花が咲かないとき
・うどんこ病にかかったとき
について、紹介します!
花が咲かない…
ヤマボウシの開花は、5~6月と言われています。
「あれ?開花時期になったのに、花が咲かない…。」とお悩みの方!
・花芽を剪定してしまっている
・鉢植えの場合、土の種類と水やりの量が合っていない
の2つの原因が考えられます。
それぞれについて、解決していきましょう!
花芽を剪定してしまっている
剪定するときに、いずれ花となる花芽を剪定してしまっている可能性が高いです!
これは花芽と葉芽を見分けることしか対処法がありません。
先ほど、剪定の際の注意するべきことでお話しした、花芽と葉芽の見分け方を覚えて、ぜひ気を付けてくださいね♪
鉢植えの場合、土の種類と水やりの量に注意
ヤマボウシはお庭に植えても、鉢に植えても、育てることができます。
特に、鉢に植えるときは、土と水やりに注意をしましょう!
水はけの良い土を使用して、土の表面が乾いたらたっぷりの水をあげることがコツです!
ヤマボウシは「木」であり、ある程度の大きさになるので、その分水も欲します。
鉢の底から染み出るくらいの水をあげましょう!
お庭で育てる際には、特に気にしなくても大丈夫です!
うどんこ病
ヤマボウシがかかる可能性のある病気、
その名も、「うどんこ病」。
どんな病気かというと、土や落ち葉に隠れている小さな小さなカビが、植物の葉に広がっていく病気です。
カビに感染した葉が、まるでうどんの白い粉をかけたようになるんです。
原因はカビなので、予防としては、
・風通しをよくする
・日当たりをよくする
ことを心がけましょう。
もしうどんこ病になってしまったら、すぐにその葉を取り除いてください!
うどんこ病は感染病なので、他の葉にも広がってしまうのです。
葉を取り除いたら、周りの葉に、「重曹スプレー」をかけてあげることをおすすめします♪
なんと重曹は、農薬取締法で、うどんこ病の散布用殺菌剤として指定されているんです!
重曹スプレーを作って吹きかけてみましょう!
・水 500~1000ml
・霧吹き用ボトル
作り方は、上記の分量の重曹と水をまぜるだけです!
霧吹き用ボトルにいれて、葉に吹きかけましょう。
基本的には、うどんこ病になったときのみの使用にしてくださいね!
花が咲かないときや、病気になったときも、焦らず適切な方法で対処することが大切です!
まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回はヤマボウシの剪定についてご紹介しました!
剪定するときは、
・冬の時期にやるということ
・花芽を切らないようにすること
に注意してくださいね♪
そして、ヤマボウシを日当たりと風通しの良いところで管理することでさらに、いきいき育てちゃってください!
お家のシンボルでもあるヤマボウシ、大切にお手入れしていきましょう!